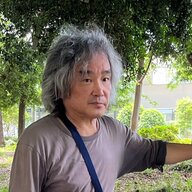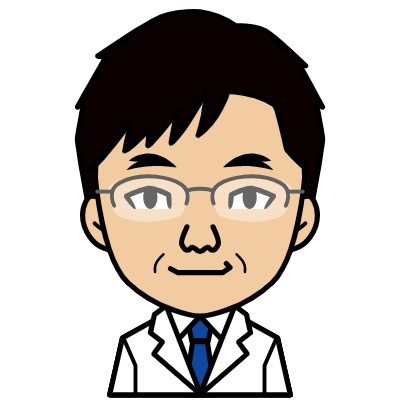💊 エイズ治療薬の開発
世界初のエイズ治療薬「AZT(アジドチミジン)」の開発。
成人T細胞白血病の研究を行っていた満屋氏が、渡米後にエイズウイルス(HIV)の研究を開始。
エイズウイルスの標的となる細胞(ヒトCD4陽性T細胞)を用いた抗ウイルス活性評価方法を確立し、AZTの開発に成功しました。
AZTは1987年に世界で初めてのエイズ治療薬として認可されました。
この発見は、かつては致死的な病であったエイズが「コントロール可能な慢性感染症」へと変貌するきっかけとなりました。
世界で2番目と3番目のエイズ治療薬の開発。
AZTに続き、ddI(ジダノシン)、ddC(ザルシタビン)も開発しました。
4番目の治療薬「ダルナビル」の開発と国際貢献。
2006年には、ダルナビルが途上国が特許料を払わずに使える医薬品として、世界で初めて国連に登録されました。これにより、エイズ治療薬が世界中で利用可能となり、多くの命が救われました。
🔬 レトロウイルス感染症治療の先駆け
レトロウイルス感染症に対して化学療法が可能であることを世界で初めて示したことが、満屋氏の最も重要な業績の一つです。
彼の研究成果が多くの新規抗ウイルス薬開発を促し、エイズ治療の劇的な進歩に貢献しました。
🧬 その他の研究と貢献
現在も先導的な研究を続け、B型肝炎ウイルスや新型コロナウイルスの治療薬開発にも貢献しています。
🎖️ 主な受賞歴
これらの輝かしい功績により、満屋氏は国内外で多数の栄誉ある賞を受賞しています。
紫綬褒章(2007年)
慶応医学賞(2007年)
読売賞
朝日賞(2015年)
日本学士院賞(2015年)
熊日賞
米国国立癌研究所所長賞
高峰記念第一三共賞(2007年)
瑞宝中綬章(2023年)
満屋氏は、熊本大学医学部を卒業後、米国国立癌研究所で要職を歴任するとともに、熊本大学特別招聘教授や国立国際医療研究センター臨床研究センター長などの要職を兼務し、日本の医学研究にも多大な貢献を続けています。
<関連する記事>
 |
「死に至る感染症」から「普通の生活が送れる病気」に―エイズ治療の歴史と現在地 …て初期の3剤は現在国立健康危機管理研究機構 国立国際医療研究所 所長の満屋裕明先生が米国NIHの研究室で開発されたものです。ほかにも日本の研究者、製薬… (出典:Medical Note) |
<関連する画像>
<ツイッターの反応>
【テリオン】【ゲーム実況者】【Gameliver】【毎日18時投稿中】【100本以上ゲームクリア済】
@Terion_game19エイズに化学療法への道を切り開いたのは、熊本大学の満屋裕明(現・国立国際医療研究センター研究所所長)が開発した、数々の薬の功績 #読書 #本