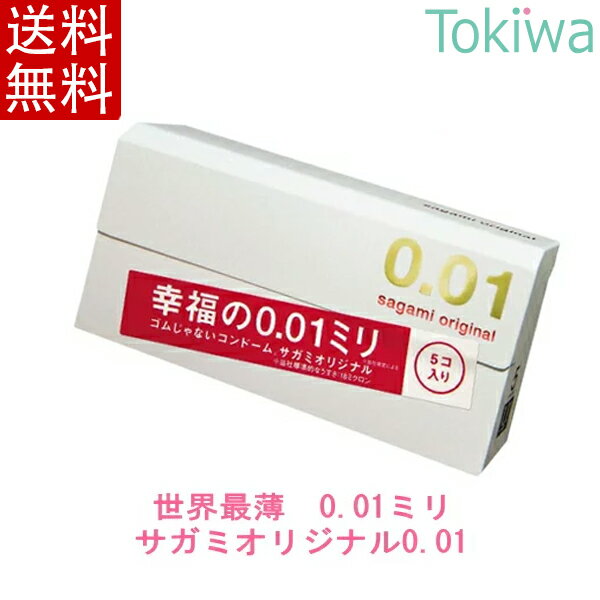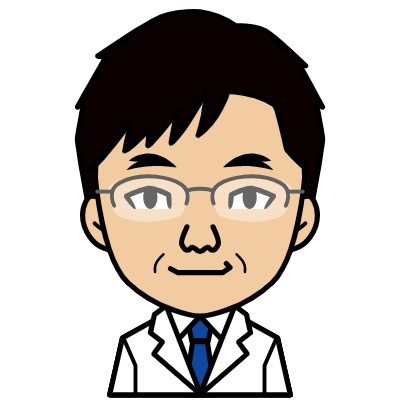| ローラ、餅つき&書き初めショット公開「素敵なお正月」「綺麗な字」と反響 …を揚げたり、書き初めをしたり、日本の文化にたくさん触れる事ができて嬉しい」と友人の家で餅つきをする様子や「土」の文字をしたためた書き初めを披露。「始ま… (出典:) |

|
書初/書初め/書き初め(かきぞめ)とは、日本の年中行事の一つで、新年になって初めて毛筆で字や絵を書くことを指す。同義語として、試毫(しごう)、試筆/始筆(しひつ)、筆始/筆始め(ふではじめ)、試簡(しかん)、試免(しめん)、試穎(しえい)、試春(ししゅん)、試觚(しこ)が、類義語として、初硯(はつす…
6キロバイト (794 語) - 2023年1月3日 (火) 02:33
|
1. 書き初めとは
歴史的に見ると、書き初めの起源については具体的な記録が少ない中、大半の説が平安時代にさかのぼると言われています。当時、貴族や僧侶にとって、文字を書くことは重要な教養の一部であり、新年に際して書道を行うことは自身の学業や技術の向上を願うための行為でもありました。「吉書」とも称されるこの習慣は、皇室や貴族の間で吉兆を願う神聖な儀式として始まったのです。
現在では、この文化は学校や家庭、文化施設でも広く実施されるようになりました。多くの学校では教育活動の一環として書き初め大会が催され、生徒たちは年始の抱負や好きな言葉を自由に選び、紙に表現します。選ばれる言葉は四字熟語や俳句、和歌など多岐に渡りますが、個々の書には書く人自身の個性や願望が込められており、毎年その表現は異なります。
さらに、書き初めには日本の伝統的な書道という芸術を継承し次世代へ伝える役割もあります。筆や墨、小筆から大筆に至るまで、書道に必要な用具すべてがこの習慣の中で取り入れられており、そのため書道の魅力もあわせて再評価されつつあります。近年では、世界的に書道の美しさやその芸術性が広く認識されつつあり、外国人からの関心も高まっています。
このように、書き初めは新年の始まりにふさわしい心のこもった行事として、人々に新たな気持ちで一年をスタートさせるきっかけを提供しています。年始に自らの手で文字を描くことで、日本の文化と伝統を再確認し、皆が新しい年へと希望を抱きます。
2. 書き初めの歴史
書き初めの行事は、「吉書(きっしょ)」とも呼ばれ、その名称は新年に吉祥を呼び込むための書として、皇室や貴族階級の間で行われたことに由来しています。この文化的な儀式は、単なる新年の祝いを超えて、祈りや願いを込めた書道の習慣として長きにわたり続けられ、日本文化の深い部分に根付いている現象とも言えます。
平安時代の書き初めは、文字を書くことが当時の社会においていかに重要視されていたかを示す象徴的な行事であり、優雅で精神的な充足をもたらすものとされていました。日本の貴族社会では、書の上達が地位や知性を表すものであったため、このような行事を通じて社会的なつながりや個人の成長が促されました。
現代においても、書き初めは学校教育や家庭の中で継続され、伝統的な書道の技術や道具の文化が次世代へと引き継がれています。書き初めは新年の抱負を表現するだけでなく、日本の豊かな歴史と文化を体現する重要な行事として、今なお様々な場所で人々に親しまれています。
3. 吉書としての書き初め
歴史的な背景を辿ると、書き初めの起源は何世紀にも遡ります。特に平安時代にその始まりを求めることができ、この時代には貴族や僧侶たちにとって書を学ぶことが教養の一部でした。正月に文字を書くことは、その後の学問の成就や書道の上達を祈念する重要な風習であり、書き初めはこのような文脈の中で活発に行われるようになりました。
書き初めが「吉書」とも称されるのは、皇室や貴族が新年に吉祥の書を行ったことがその由来です。このため、書き初めは新しい年の祈りを込め、また同時に幸福を招く意図を持つ行為としても大切にされてきました。この伝統は、現代においても続いており、特に正月の三が日、1月2日に行われることが一般的です。学校や文化施設、家庭においても、新年を迎える行事の一環として親しまれています。
現代の書き初めでは、書く内容は実に多様です。年始の抱負や好きな言葉、熟語や俳句、和歌が多く選ばれます。書き初めの際に心を込めて書かれるこれらの文字は、その年の抱負を具体的にし、また実現への第一歩を踏み出すきっかけとされます。そして、それぞれの書に込められる願いは書き手の個性を反映し、毎年新鮮な驚きを与えてくれるのです。
このような書き初め文化は、日本の伝統的な書道の道具や技法を保存し、継承するための重要な役割を果たしています。また近年、書道の普及に伴って、その美しさや芸術性が国内外で再評価されるようになってきました。書き初めを通じて、日本の文化や伝統を見直し、新たな始まりを迎えるにあたり私たちに深い意義と魅力を教えてくれます。
4. 現代の書き初めの風習
正月の三が日、特に1月2日に書き初めを行う風習は、多くの地域で受け継がれ、学校や文化施設、個々の家庭で実施されているのです。
書き初めは単なる伝統行事に留まらず、現代においても新年に対する人々の特別な思いや願いを表現する重要な文化活動として位置づけられています。
\n\nこの風習において、参加者は年始の抱負や希望、時には好きな四字熟語や俳句を書きます。
それぞれの選ばれた言葉には、書く人自身の新年に対する期待や決意が込められており、書き初めをすること自体が一種の自己表現の場となっています。
例えば、小学校では年始の授業の一環として、子供たちが一生懸命に自分の決意を表す漢字や言葉を書き、そこには未来に対する無限の可能性と希望の光が感じられるでしょう。
\n\n加えて、書き初めは書道文化の振興にも大きく貢献しています。
筆や墨、紙といった書道の基本的な道具を使用することで、日本の伝統文化に触れる入り口ともなり、近年ではその芸術的な側面が国内外で改めて評価されています。
\n\n家庭で行う書き初めでは、家族間で書いた言葉を見せ合うことで、互いの新年の目標や思いを共有する貴重な時間が生まれます。
これにより、書き初めは単なる習慣から、家族や友人同士の絆を深めるきっかけとして、日本人特有のあたたかい新年の始まりを提供しているのです。
現代の書き初めには、新年に対する個々の気持ちを込めたこの文化が、これからも愛され続けていくでしょう。
5. まとめ
書き初めは、新年の抱負を紙に書くという行為を通じて、新たな一年のスタートを切るための大切な儀式とされています。
特にこの行事は、学校や家庭で盛んに行われ、多くの教育機関では教育活動の一環として取り入れられています。
\n\n歴史的に見て、書き初めは平安時代にその起源を持つとされ、当時は貴族や僧侶たちが新年を迎えるに際して神聖な書を書くことで翌年の学業や芸術の成功を祈ったと伝えられています。
このような歴史背景から、書き初めは単なる習慣ではなく、新しい年に向けた深い意味と祈りが込められた文化的行事といえるでしょう。
\n\n現代において書き初めは、新年の三が日、特に1月2日に行われることが多く、その風景は日本の正月の一部として多くの人々に親しまれています。
書かれる文字や言葉は、個々の願いを反映したものであり、毎年異なる様相を見せています。
また、書道といえば筆と墨を使用する日本独自の文化の継承とも密接に関わっており、この行事を通じて次世代へとその魅力を伝えていくことが重要です。
\n\n近年では、書き初めはただの文字を書く行為ではなく、日本の伝統文化の奥深さや、その美しさを再認識する素晴らしい機会としても評価されています。
また、書道の芸術性が世界的にも認知されるようになり、書き初めを行うことで、国内外にかかわらず、多くの人々が日本の文化に触れるきっかけとなっています。
\n\n書き初めという古くから伝わる行事を通じて、私たちは毎年再び、私たち自身の内にある希望や夢を見つめ直し、新たなステップを踏み出すことができるのです。